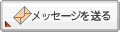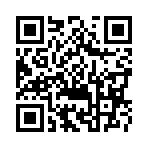2012年11月19日
戦後警察けん銃について (証言編)
戦後日本警察のけん銃事情について。各方面からの聞き取りをメモ書き。
【① K視庁警察官】
・M1917について
「K視庁では平成に入ってからも使われていた。主に機動隊と、交通課の警察官など、普段けん銃を携帯しない部署の人間が使っていた。自分も平成初期に交通課勤務の際に渡されていた。非常に大きく使い勝手は悪い。ハーフムーンクリップだけでなく、フルムーンクリップもあった。けん銃入れは白色のものではなく自ら隊のお下がりの黒色の銃把が見えるタイプを使っていた。機動隊は昭和後期は昔ながらの可動しないものを使っていたが、これも「自ら」のお下がりだと思うが、平成に入ってからは機動隊も乗車時に可動して邪魔にならない『乗車用』でM1917をぶら下げていた」
・M1917のグリップアダプターについて
「K視庁のM1917にはゴム製のグリップアダプターが付けられていた。また、グリップは木製のものではなく、メダリオンのないチェッカリングの入った茶色い樹脂製のグリップが付けられていて、オリジナルよりも大きく、親指がグリップに乗るような縦方向に延長されたグリップが付けられていた。ハドソン?だかのモデルガンにそっくりなグリップがついているのを見たことがある」
・M10について
「M10は平成に入ってからも普段けん銃を携行しない課長や署長用として使われていた。ニューナンブの3インチよりもミリポリの4インチの方が見栄えがいいし、けん銃入れも大きくてサマになる」
・ガバメントについて
「平成に入ってからも使われていたM1917に比べてガバメントの方が先に使用されなくなったようだ。ブルーイングされていたシリーズ70?(※かつての月刊GUN誌の記事に「病院で一緒になった警察署長の腰のガバメントのブルーイングが目に眩しかった」という記事から「シリーズ70輸入説」があった)あれは米国から支給された『ミリガバ』の再処理だと思う。日頃けん銃を携行している外勤警官はけん銃の手入れをする暇などなく、下手に手入れなんてしようものなら銃刀法の『銃を弄ぶ』ということにもなりかねないから、保管庫で渡されて、戻してと、毎日繰り返すだけだから、外勤警察官のけん銃の状態は思いのほか悪い。すぐ錆が浮く。オーバーホールの際に表面の再処理を行うんだが、ニューナンブにしても再処理の関係でブルーイング、黒染め、パーカーライズといろいろあって、『青いガバ』もこれと同じだと思う」
・コルトポケット(32オート)について
「平成の10年代まで婦人警官や刑事が使っていたはずだ」
(ガバメントやコルトポケットなどの自動式拳銃は部品点数が多く、製造から時間が経ち交換部品の入手性などから早く消えたとも考えられる。安全管理上もガバメントやコルトポケットの場合、「安全ゴム」が使用できないなどの理由もあった?)

※ コルト ディテクティブ
・コルト38口径(回転式)について
「いまでも射撃訓練でいろんな部署の人間が揃って、横一列に数十人が並んで射撃するわけだ。ニューナンブなんかとコルトはシリンダーの回転方向が違うから訓練の際に『コルトの人は手を挙げてください』と、指示が飛ぶと、いまでも数十人中の3人くらいは私服が手を挙げる。どれも2インチだ」
(コルトディテクティブと、派生モデルのコブラは外見が酷似しており、どちらかは不明)
・ランヤードリングのアルミ?円盤について
「あれはうちでは保管中のけん銃に付けられていた。『この銃は弾が入っていませんよ』という表示だったはず」

(※ 平成初期の大阪府警の通常点検の様子。手前はバレルシェラウドの形状等からコルトディテクティブの後継機種であるコルトコブラと考えられる。組事務所への「ガサ」の為、防弾チョッキを着用。ランヤードリングには金属製の円盤が確認できる)
【② N県警OB】
・いままで使用したけん銃について
「警察官を拝命して所轄に配属された昭和50年代初頭には38口径の6発入るコルトを下げていた。いまでも思い出すな。交番勤務だったときに、いまじゃ有名な拉致事件の被害者がいなくなって、当初は誘拐事件として捜査した。38口径ぶら下げて警丈もって『山狩り』したな。蓋のないけん銃入れで下げてたが、あれ、銃が汚れるんだな。雨なんか降ったら錆びる訳だ。警備に行ってからも4インチの6発のコルトコマンドを使ってたな。滅多にぶら下げることはなかったけど、『コリ●ン●ート』の警報が出て、工●船の潜脱する海岸で張るわけだ。場所なんか決まってるから、だいたい当たる。沖で発光信号が光るだろ?拳銃握りしめて海岸で連中を待ったこともあったな。SPになってからはコルトポケットを使ってた。年季もんだぞ。けれど小型で名前の通り、スーツのポケットにも入るし、反動も小さい。わるくないけん銃だった。コルトポケットはうちの県警では平成10年くらいまでは使ってたはずだ。ちなみに警衛警備でK視庁のSPが出張ってくるときにけん銃を見たら、連中はチーフスペシャルの2インチを使ってたな」

※ コルト コマンド

※ コルト ポリスポジティブ
(コルトコマンドはコルトポリスポジティブのパーカー処理され、各部の工作を簡易化したものであり、外見は酷似。コマンドは米軍部隊向けに製造されたけん銃であり、米国貸与けん銃のひとつか?)
・45口径について
「当時、N署(※ 当地の1線署)でも昭和50年代まで結構45口径はあったな。回転式と自動式があったが、所轄の外勤でも自動式をぶら下げてる奴も結構いた。刑事の間でも45口径は重いけど、人気があってね。当時、科警研だかが調べたんだよ。俺たちがけん銃を使うような局面っていうのは、銃撃戦じゃないんだ。ヤー公とかがポン刀で斬りかかってきたとするだろ?そうなった時の交戦距離なんて言うのはほんの数メートルなわけだ。38口径で『ババン!』と撃って当たったとしても、38口径だと相手は倒れず、こっちも一太刀喰らっちまうわけだ。けれど、45口径なんて言うのは一発当たれば大の大人も吹っ飛ぶ。『いざというときは45口径』っていう風潮はあったよな。ま、滅多に使うことはないんだけど」
(歴史は繰り返すということか?どこかで聞いた100年以上前のフィリピンのような話だ)

※ コルト 45口径 自動式 (M1911A1)

※ コルト 45口径 回転式 (M1917)
・外勤が「一発でぶっ倒れる45口径」で、SPがコルトポケットですか?(笑)
「言われてみれば確かに逆だよな(笑)」
・ニューナンブについて
「ナンブがくるまで結構時間がかかった。昭和50年代でいったら、うちの署なんて何丁もなかったんじゃない?ほとんどが銃身の長い(※4インチのことをいってる雰囲気)38口径か、45口径だったもんな。変わったところではマスターピースなんていうのもあった。たしかスミスアンドウエッソンだ」

※ S&W M15 マスターピース?詳細は不明
・けん銃入れについて
45口径が多かったころはグリップ丸見えのけん銃入れでぶら下げてたけど、途中で「雨でけん銃が錆びる」っていうんで、蓋付になった。
【③ F県警警察官】
・いままで使用したけん銃について
「エアウェイト、P230は触ったこともなく、初任科からいまのいままで一貫してニューナンブの3インチです。機関けん銃も触りましたが、けん銃はニューナンブだけですね。ゴールデンベアは見ただけです。警察学校にも平成10年代後半に45口径などはなかったですね」
・ニューナンブ以外のけん銃について
「初任科の時に教官から『校長の銃はでっかいぞ』と見せられたのがこれ(※M10 4インチ)でしたね。いまはマル機ですが、知る限りうちの部隊は全員がニューナンブの3インチですね。ちなみに通常の警備で機動隊員はけん銃は携行しません。常時携行はC県の空●隊くらいです」

(S&W M10 4インチ)
・ランヤードリングのアルミ?円盤について
「あれはF県警では勤務中もぶら下がっていたと思いますね。たしか貸与者の氏名が書かれていたと思います」
――上記以外の人間に話を聞いても、鉄道公安官が使用していたコルトオフィシャルポリスの名前は現場警察官からは出ず、いきおい飛び出したコマンド?マスターピース?21世紀も10年以上経って32オート??
聞けば聞くほどに泥沼化する「戦後日本のお役所けん銃史」であるが、終戦直後~昭和20年代はカオスすぎてまったく収拾がつかないので、昭和後期まで使われていたけん銃の主なものについて概要を記すと、
・S&W M1917 / COLT M1917
かなりの数が米国から譲渡されたと考えられ昭和後期ではニューナンブに次ぐ量であったと模様。警視庁でも長年使われ、平成期に入ってから廃棄処分されたものと考えられる。最後期はグリップアダプターに、樹脂製銃把であった。「廃棄のホルスターの量も圧倒的に数が多かった。多すぎて銭湯の薪として燃やしていた」(元払下げ業者)。また、COLT M1917も存在したが、数は少なかったという。
・COLT M1911 および 各社M1911A1
M1917とともに米国より貸与されたが、全体の数としては少数で「射撃訓練で見かけると物珍しさから話題になった」と言い、県警ごとによるばらつきはあったとしても、元払下げ業者も「ガバ用のけん銃入れはごく少数だったし、けん銃つりひものオート用自体、すごく数が少なかった」といい、数は決して多くなかったと考えられる。「あさま山荘事件」では機動隊が使用。コルト以外のM1911A1の目撃情報もあり。
※ (追記) 平成5年埼玉県警年頭視閲式での装備を確認。新制服導入後も群馬県警での使用を確認。
・S&W Military&Police
通称「ビクトリーモデル」。M1917に次ぐ量を米国から貸与、その後に譲渡されたと考えられ、放出されたけん銃ケースを見ても4インチ、5インチがともに装備されていたことがわかる。「けん銃入れの蓋付化」が行われた昭和48年以降に製造されたけん銃入れも多く存在し、平成20年代(!)でも使われていた痕跡がある。
・S&W Chief Specialシリーズ
戦後の警官増員時に行われたけん銃の整備で輸入された。制服警察官は3インチを、私服警察官が2インチを使用していた模様。3インチはスクエアバッドの目撃例が多く、現在も一部の交機隊などで使用されている模様。
・S&W M10シリーズ
戦後の警官増員時に行われたけん銃の整備で輸入された模様。現在でも一部で使用中。M15「コンバットマスターピース」、M13「FBIモデル」を使用していたとの情報もあり。
・COLT Detective、POLICE POSITIVEシリーズ
ディテクティブ系が米国貸与で支給されたのか、戦後の輸入なのかは不明。しかし、Detectiveは1927年に発売されており、姉妹モデルであるポリスポジティブなどとともに米国貸与けん銃の可能性大。COBRAは1950年の発売であり、輸入と考えられる。近年、SIG P230等に更新されるも、現在もDetective(2インチ)シリーズは私服捜査員が使用中。コマンドなどのPOLICE POSITIVE(4インチ)シリーズはDetectiveシリーズよりも先に廃棄処分となったものと考えられる。またかつての鉄道公安官はPOLICE POSITIVEと外観上酷似したコルトオフィシャルポリスを装備しており、国鉄の分割民営化で鉄道公安官制度は警察に吸収されたことでコルトオフィシャルポリスも警察に引き継がれたと考えられるが詳細不明。
・COLT M1908 (32AUTO)
1949年(昭和24)7月15日付のGHQによる指示による米国からの貸与けん銃なのか、それ以前の支給品なのかが不明。COLT 32AUTOとともにFN ブローニングM1910、コルトポケット(25オート)などの自動拳銃も装備されたが、戦前の警察/旧日本軍が使用→敗戦で接収→GHQから再貸与なのか、米国内で使用したものを貸与したのか、はたまたその両方なのかが不明。「警察史」などの資料では昭和40年代の刑事が持っている写真が複数見つかる。SPを含む私服捜査員が多数使用していた模様。また一部の婦警、交通係も持っていたとの証言もあり。近年、SIG P230等に更新された模様。
・FN M1910シリーズ
「32オート」と同じく、警視庁をはじめ戦時中?から使用されており、1949年(昭和24)7月15日付のGHQによる指示による米国からのけん銃が貸与なのか、それ以前に旧軍接収けん銃の南部十四年式、九四式、二十六年式けん銃などと共に支給品されたものなのかが不明。近年、SIG P230等に更新された模様。
・コルトポケット (25AUTO)
こちらも昭和後期から平成10年ごろ?まで婦人警察官などの使用が確認されているが、戦前の警察/旧日本軍が使用→敗戦で接収→GHQから再貸与なのか、米国内で使用したものを貸与したのか、はたまたその両方なのか不明。
――「戦後日本警察」。実は相当のカオスである。
【① K視庁警察官】
・M1917について
「K視庁では平成に入ってからも使われていた。主に機動隊と、交通課の警察官など、普段けん銃を携帯しない部署の人間が使っていた。自分も平成初期に交通課勤務の際に渡されていた。非常に大きく使い勝手は悪い。ハーフムーンクリップだけでなく、フルムーンクリップもあった。けん銃入れは白色のものではなく自ら隊のお下がりの黒色の銃把が見えるタイプを使っていた。機動隊は昭和後期は昔ながらの可動しないものを使っていたが、これも「自ら」のお下がりだと思うが、平成に入ってからは機動隊も乗車時に可動して邪魔にならない『乗車用』でM1917をぶら下げていた」
・M1917のグリップアダプターについて
「K視庁のM1917にはゴム製のグリップアダプターが付けられていた。また、グリップは木製のものではなく、メダリオンのないチェッカリングの入った茶色い樹脂製のグリップが付けられていて、オリジナルよりも大きく、親指がグリップに乗るような縦方向に延長されたグリップが付けられていた。ハドソン?だかのモデルガンにそっくりなグリップがついているのを見たことがある」
・M10について
「M10は平成に入ってからも普段けん銃を携行しない課長や署長用として使われていた。ニューナンブの3インチよりもミリポリの4インチの方が見栄えがいいし、けん銃入れも大きくてサマになる」
・ガバメントについて
「平成に入ってからも使われていたM1917に比べてガバメントの方が先に使用されなくなったようだ。ブルーイングされていたシリーズ70?(※かつての月刊GUN誌の記事に「病院で一緒になった警察署長の腰のガバメントのブルーイングが目に眩しかった」という記事から「シリーズ70輸入説」があった)あれは米国から支給された『ミリガバ』の再処理だと思う。日頃けん銃を携行している外勤警官はけん銃の手入れをする暇などなく、下手に手入れなんてしようものなら銃刀法の『銃を弄ぶ』ということにもなりかねないから、保管庫で渡されて、戻してと、毎日繰り返すだけだから、外勤警察官のけん銃の状態は思いのほか悪い。すぐ錆が浮く。オーバーホールの際に表面の再処理を行うんだが、ニューナンブにしても再処理の関係でブルーイング、黒染め、パーカーライズといろいろあって、『青いガバ』もこれと同じだと思う」
・コルトポケット(32オート)について
「平成の10年代まで婦人警官や刑事が使っていたはずだ」
(ガバメントやコルトポケットなどの自動式拳銃は部品点数が多く、製造から時間が経ち交換部品の入手性などから早く消えたとも考えられる。安全管理上もガバメントやコルトポケットの場合、「安全ゴム」が使用できないなどの理由もあった?)

※ コルト ディテクティブ
・コルト38口径(回転式)について
「いまでも射撃訓練でいろんな部署の人間が揃って、横一列に数十人が並んで射撃するわけだ。ニューナンブなんかとコルトはシリンダーの回転方向が違うから訓練の際に『コルトの人は手を挙げてください』と、指示が飛ぶと、いまでも数十人中の3人くらいは私服が手を挙げる。どれも2インチだ」
(コルトディテクティブと、派生モデルのコブラは外見が酷似しており、どちらかは不明)
・ランヤードリングのアルミ?円盤について
「あれはうちでは保管中のけん銃に付けられていた。『この銃は弾が入っていませんよ』という表示だったはず」

(※ 平成初期の大阪府警の通常点検の様子。手前はバレルシェラウドの形状等からコルトディテクティブの後継機種であるコルトコブラと考えられる。組事務所への「ガサ」の為、防弾チョッキを着用。ランヤードリングには金属製の円盤が確認できる)
【② N県警OB】
・いままで使用したけん銃について
「警察官を拝命して所轄に配属された昭和50年代初頭には38口径の6発入るコルトを下げていた。いまでも思い出すな。交番勤務だったときに、いまじゃ有名な拉致事件の被害者がいなくなって、当初は誘拐事件として捜査した。38口径ぶら下げて警丈もって『山狩り』したな。蓋のないけん銃入れで下げてたが、あれ、銃が汚れるんだな。雨なんか降ったら錆びる訳だ。警備に行ってからも4インチの6発のコルトコマンドを使ってたな。滅多にぶら下げることはなかったけど、『コリ●ン●ート』の警報が出て、工●船の潜脱する海岸で張るわけだ。場所なんか決まってるから、だいたい当たる。沖で発光信号が光るだろ?拳銃握りしめて海岸で連中を待ったこともあったな。SPになってからはコルトポケットを使ってた。年季もんだぞ。けれど小型で名前の通り、スーツのポケットにも入るし、反動も小さい。わるくないけん銃だった。コルトポケットはうちの県警では平成10年くらいまでは使ってたはずだ。ちなみに警衛警備でK視庁のSPが出張ってくるときにけん銃を見たら、連中はチーフスペシャルの2インチを使ってたな」

※ コルト コマンド

※ コルト ポリスポジティブ
(コルトコマンドはコルトポリスポジティブのパーカー処理され、各部の工作を簡易化したものであり、外見は酷似。コマンドは米軍部隊向けに製造されたけん銃であり、米国貸与けん銃のひとつか?)
・45口径について
「当時、N署(※ 当地の1線署)でも昭和50年代まで結構45口径はあったな。回転式と自動式があったが、所轄の外勤でも自動式をぶら下げてる奴も結構いた。刑事の間でも45口径は重いけど、人気があってね。当時、科警研だかが調べたんだよ。俺たちがけん銃を使うような局面っていうのは、銃撃戦じゃないんだ。ヤー公とかがポン刀で斬りかかってきたとするだろ?そうなった時の交戦距離なんて言うのはほんの数メートルなわけだ。38口径で『ババン!』と撃って当たったとしても、38口径だと相手は倒れず、こっちも一太刀喰らっちまうわけだ。けれど、45口径なんて言うのは一発当たれば大の大人も吹っ飛ぶ。『いざというときは45口径』っていう風潮はあったよな。ま、滅多に使うことはないんだけど」
(歴史は繰り返すということか?どこかで聞いた100年以上前のフィリピンのような話だ)

※ コルト 45口径 自動式 (M1911A1)

※ コルト 45口径 回転式 (M1917)
・外勤が「一発でぶっ倒れる45口径」で、SPがコルトポケットですか?(笑)
「言われてみれば確かに逆だよな(笑)」
・ニューナンブについて
「ナンブがくるまで結構時間がかかった。昭和50年代でいったら、うちの署なんて何丁もなかったんじゃない?ほとんどが銃身の長い(※4インチのことをいってる雰囲気)38口径か、45口径だったもんな。変わったところではマスターピースなんていうのもあった。たしかスミスアンドウエッソンだ」

※ S&W M15 マスターピース?詳細は不明
・けん銃入れについて
45口径が多かったころはグリップ丸見えのけん銃入れでぶら下げてたけど、途中で「雨でけん銃が錆びる」っていうんで、蓋付になった。
【③ F県警警察官】
・いままで使用したけん銃について
「エアウェイト、P230は触ったこともなく、初任科からいまのいままで一貫してニューナンブの3インチです。機関けん銃も触りましたが、けん銃はニューナンブだけですね。ゴールデンベアは見ただけです。警察学校にも平成10年代後半に45口径などはなかったですね」
・ニューナンブ以外のけん銃について
「初任科の時に教官から『校長の銃はでっかいぞ』と見せられたのがこれ(※M10 4インチ)でしたね。いまはマル機ですが、知る限りうちの部隊は全員がニューナンブの3インチですね。ちなみに通常の警備で機動隊員はけん銃は携行しません。常時携行はC県の空●隊くらいです」

(S&W M10 4インチ)
・ランヤードリングのアルミ?円盤について
「あれはF県警では勤務中もぶら下がっていたと思いますね。たしか貸与者の氏名が書かれていたと思います」
――上記以外の人間に話を聞いても、鉄道公安官が使用していたコルトオフィシャルポリスの名前は現場警察官からは出ず、いきおい飛び出したコマンド?マスターピース?21世紀も10年以上経って32オート??
聞けば聞くほどに泥沼化する「戦後日本のお役所けん銃史」であるが、終戦直後~昭和20年代はカオスすぎてまったく収拾がつかないので、昭和後期まで使われていたけん銃の主なものについて概要を記すと、
・S&W M1917 / COLT M1917
かなりの数が米国から譲渡されたと考えられ昭和後期ではニューナンブに次ぐ量であったと模様。警視庁でも長年使われ、平成期に入ってから廃棄処分されたものと考えられる。最後期はグリップアダプターに、樹脂製銃把であった。「廃棄のホルスターの量も圧倒的に数が多かった。多すぎて銭湯の薪として燃やしていた」(元払下げ業者)。また、COLT M1917も存在したが、数は少なかったという。
・COLT M1911 および 各社M1911A1
M1917とともに米国より貸与されたが、全体の数としては少数で「射撃訓練で見かけると物珍しさから話題になった」と言い、県警ごとによるばらつきはあったとしても、元払下げ業者も「ガバ用のけん銃入れはごく少数だったし、けん銃つりひものオート用自体、すごく数が少なかった」といい、数は決して多くなかったと考えられる。「あさま山荘事件」では機動隊が使用。コルト以外のM1911A1の目撃情報もあり。
※ (追記) 平成5年埼玉県警年頭視閲式での装備を確認。新制服導入後も群馬県警での使用を確認。
・S&W Military&Police
通称「ビクトリーモデル」。M1917に次ぐ量を米国から貸与、その後に譲渡されたと考えられ、放出されたけん銃ケースを見ても4インチ、5インチがともに装備されていたことがわかる。「けん銃入れの蓋付化」が行われた昭和48年以降に製造されたけん銃入れも多く存在し、平成20年代(!)でも使われていた痕跡がある。
・S&W Chief Specialシリーズ
戦後の警官増員時に行われたけん銃の整備で輸入された。制服警察官は3インチを、私服警察官が2インチを使用していた模様。3インチはスクエアバッドの目撃例が多く、現在も一部の交機隊などで使用されている模様。
・S&W M10シリーズ
戦後の警官増員時に行われたけん銃の整備で輸入された模様。現在でも一部で使用中。M15「コンバットマスターピース」、M13「FBIモデル」を使用していたとの情報もあり。
・COLT Detective、POLICE POSITIVEシリーズ
ディテクティブ系が米国貸与で支給されたのか、戦後の輸入なのかは不明。しかし、Detectiveは1927年に発売されており、姉妹モデルであるポリスポジティブなどとともに米国貸与けん銃の可能性大。COBRAは1950年の発売であり、輸入と考えられる。近年、SIG P230等に更新されるも、現在もDetective(2インチ)シリーズは私服捜査員が使用中。コマンドなどのPOLICE POSITIVE(4インチ)シリーズはDetectiveシリーズよりも先に廃棄処分となったものと考えられる。またかつての鉄道公安官はPOLICE POSITIVEと外観上酷似したコルトオフィシャルポリスを装備しており、国鉄の分割民営化で鉄道公安官制度は警察に吸収されたことでコルトオフィシャルポリスも警察に引き継がれたと考えられるが詳細不明。
・COLT M1908 (32AUTO)
1949年(昭和24)7月15日付のGHQによる指示による米国からの貸与けん銃なのか、それ以前の支給品なのかが不明。COLT 32AUTOとともにFN ブローニングM1910、コルトポケット(25オート)などの自動拳銃も装備されたが、戦前の警察/旧日本軍が使用→敗戦で接収→GHQから再貸与なのか、米国内で使用したものを貸与したのか、はたまたその両方なのかが不明。「警察史」などの資料では昭和40年代の刑事が持っている写真が複数見つかる。SPを含む私服捜査員が多数使用していた模様。また一部の婦警、交通係も持っていたとの証言もあり。近年、SIG P230等に更新された模様。
・FN M1910シリーズ
「32オート」と同じく、警視庁をはじめ戦時中?から使用されており、1949年(昭和24)7月15日付のGHQによる指示による米国からのけん銃が貸与なのか、それ以前に旧軍接収けん銃の南部十四年式、九四式、二十六年式けん銃などと共に支給品されたものなのかが不明。近年、SIG P230等に更新された模様。
・コルトポケット (25AUTO)
こちらも昭和後期から平成10年ごろ?まで婦人警察官などの使用が確認されているが、戦前の警察/旧日本軍が使用→敗戦で接収→GHQから再貸与なのか、米国内で使用したものを貸与したのか、はたまたその両方なのか不明。
――「戦後日本警察」。実は相当のカオスである。