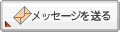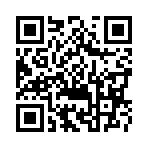2014年03月25日
戦後警察けん銃について (資料編/皇宮警察史)
ひさしぶりのブログ更新。
今回は「皇宮警察史」を中心に戦後警察けん銃に関係する研究の中間報告。
皇宮警察本部の英訳は「Imperial Guard Headquarters」。
その名が示す通り「皇室守護を目的とした国家機関」であり、その活動は皇居をはじめとした皇室関連施設であり、皇宮警察では一般の警察官が行う交通違反の取り締まりや、街頭での職務質問等の防犯活動などの警察活動の多くを行わず「お濠の中」で「日本の象徴及び国民統合の象徴である天皇陛下と皇族」をお護りし、皇室行事では儀礼服を着込んで皇室行事の一部として儀仗任務に就くなど、さまざまな特殊性を持つ警察組織である。

皇宮警察本部前に整列して記念写真に写る皇宮護衛官。巡査、巡査部長の階級章が上腕部。警部補以上は消防官風の階級章が右胸につく「昭和22年改正」(小改正を除く)であることから、「昭和31年改正」以前の冬服であることがわかる。

比較的後年に撮影されたと考えられる儀礼服での記念写真。
そんな皇宮警察本部が纏めた「皇宮警察史」(1976年版)より以下、抜粋。
「(皇宮警察では)拳銃は戦前からブローニングを携帯していたが、二十七年十月二十四日(中略)側衛員を除き十月十日からこれをチーフス・スペシャルに替え、さらに三十年六月一日から、SW三八レギュラー・レボルバー五吋けん銃に替え、併せてけん銃つり紐を使用することとした」
「ついで三十一年八月一日、(皇宮護衛官)全員に拳銃を個人貸与し、それによって拳銃取扱いに習熟して事故を防止し、愛護心を涵養し、員数不足による不便の解消と同一種による整一化を期した。しかし同回転式拳銃は米軍の軍用拳銃を活用したもので、形式・性能等の面で必ずしも適正なものではなかった」

「葉山御用邸正門にて(27.8)」 昭和27年。進駐軍由来のカーキ色の「チノパン、チノシャツ」を国産化したカーキ色の盛夏衣時代

「「儀礼服に身を包み」 昭和25年」
――つまり、昭和27年にそれまで皇宮警察で使用していたブローニングからチーフスペシャルに「側衛員」をのぞいて支給したが、早くも3年後の昭和30年からは「SW三八レギュラー・レボルバー五吋けん銃」(S&W レギュレーションポリス)に代替――さらに翌31年に「全員に拳銃を個人貸与」したが、そこで貸与されたけん銃は「米軍の軍用回転式拳銃」(S&W ミリポリビクトリーモデルか?)だったと「皇宮警察史」は語る――いささか錯綜した記述であるが、要点を整理すれば、
【戦前~昭和27年】 ブローニング自動式 (※ 側衛員用)

【昭和27年~30年】 S&W チーフススペシャル (※ 側衛員はブローニング)


【昭和30年~31年】 S&W レギュレーションポリス

【昭和31年~ 】 S&W ミリポリビクトリーモデル ないし S&W M1917、COLT M1917


「側衛員を除き十月十日からこれをチーフス・スペシャル」に更新されたという記述からも、いわゆる「制服警察官」の皇宮護衛官がチーフス → レギュレーションポリス → ミリポリビクトリー?に代替されても、いわゆる「SP」的な任務を与えられている「側衛員」はブローニングを使用し続けられたと考えられる。
皇宮警察史はつづける。
「日本人の体格に合うよう若干小型化し、しかも性能もすぐれた「ニューナンブ」をわが国で製作し、国産の「ニューナンブ」を製作。皇宮警察でも四十四年十二月二十六日、二十二丁を採用し、儀仗隊員に携帯させ、以降徐々に増加させている」
以上の記述からも皇宮警察ではニューナンブM60の採用は、制式化された昭和35年から9年も経った昭和44年(1969年)からであることがわかり、新けん銃への切り替えも一斉ではなく「徐々に増加」。つまり、昭和44年以降も米軍軍用回転式けん銃と併用されたことが伺えるが、昭和天皇が崩御された際の「大喪の礼」警備では、ニューナンブ以外の旧型けん銃を携行する護衛官が多数目撃されており「皇宮警察史」のいう「昭和31年同一銃種による整一化を期した」という「整一化」が、「現場の護衛官」を指すのか?「皇宮警察全体」を指すのか?はっきりせず、後年までに整一化が完了したかについては――はなはだ疑問が残る。

参考。近年撮影された「32ワルサーPPK」を携行する制服姿の皇宮護衛官。皇宮護衛官のけん銃つりひもは伝統的に臙脂色のものが用いられている。
しかし、そのなかでも各県警本部史などの資料を突き合わせると「実包の共通化」を図るべく、雑多なけん銃と弾薬のうち、45口径をその大きさと重さから敬遠し、弾種を「38SPL」で統一しようとしていたフシがあり、ニューナンブとの使用弾薬が共通であることから、近年までミリポリビクトリーモデルが日本警察では使用され続け、さらに「操作、動作の異なるコルト式けん銃の評判は良くなかった」ということからも、「皇宮警察史」のいう「昭和31年の米軍軍用回転式拳銃による同一銃種による整一化」は日本警察に大量に譲渡(当初は貸与)されたS&W ミリタリーポリスビクトリーモデルであったと考えられるが、戦後にわざわざ輸入した「チーフス」はどこへ行ったのか?その後に導入されたS&W レギュレーションポリスの行方は?それらは他本部へ管理替え?――と、ひとつの事実がわかれば新たな謎がやっぱり生まれる戦後警察けん銃の調査なのであった。
今回は「皇宮警察史」を中心に戦後警察けん銃に関係する研究の中間報告。
皇宮警察本部の英訳は「Imperial Guard Headquarters」。
その名が示す通り「皇室守護を目的とした国家機関」であり、その活動は皇居をはじめとした皇室関連施設であり、皇宮警察では一般の警察官が行う交通違反の取り締まりや、街頭での職務質問等の防犯活動などの警察活動の多くを行わず「お濠の中」で「日本の象徴及び国民統合の象徴である天皇陛下と皇族」をお護りし、皇室行事では儀礼服を着込んで皇室行事の一部として儀仗任務に就くなど、さまざまな特殊性を持つ警察組織である。

皇宮警察本部前に整列して記念写真に写る皇宮護衛官。巡査、巡査部長の階級章が上腕部。警部補以上は消防官風の階級章が右胸につく「昭和22年改正」(小改正を除く)であることから、「昭和31年改正」以前の冬服であることがわかる。
比較的後年に撮影されたと考えられる儀礼服での記念写真。
そんな皇宮警察本部が纏めた「皇宮警察史」(1976年版)より以下、抜粋。
「(皇宮警察では)拳銃は戦前からブローニングを携帯していたが、二十七年十月二十四日(中略)側衛員を除き十月十日からこれをチーフス・スペシャルに替え、さらに三十年六月一日から、SW三八レギュラー・レボルバー五吋けん銃に替え、併せてけん銃つり紐を使用することとした」
「ついで三十一年八月一日、(皇宮護衛官)全員に拳銃を個人貸与し、それによって拳銃取扱いに習熟して事故を防止し、愛護心を涵養し、員数不足による不便の解消と同一種による整一化を期した。しかし同回転式拳銃は米軍の軍用拳銃を活用したもので、形式・性能等の面で必ずしも適正なものではなかった」
「葉山御用邸正門にて(27.8)」 昭和27年。進駐軍由来のカーキ色の「チノパン、チノシャツ」を国産化したカーキ色の盛夏衣時代

「「儀礼服に身を包み」 昭和25年」
――つまり、昭和27年にそれまで皇宮警察で使用していたブローニングからチーフスペシャルに「側衛員」をのぞいて支給したが、早くも3年後の昭和30年からは「SW三八レギュラー・レボルバー五吋けん銃」(S&W レギュレーションポリス)に代替――さらに翌31年に「全員に拳銃を個人貸与」したが、そこで貸与されたけん銃は「米軍の軍用回転式拳銃」(S&W ミリポリビクトリーモデルか?)だったと「皇宮警察史」は語る――いささか錯綜した記述であるが、要点を整理すれば、
【戦前~昭和27年】 ブローニング自動式 (※ 側衛員用)

【昭和27年~30年】 S&W チーフススペシャル (※ 側衛員はブローニング)


【昭和30年~31年】 S&W レギュレーションポリス

【昭和31年~ 】 S&W ミリポリビクトリーモデル ないし S&W M1917、COLT M1917


「側衛員を除き十月十日からこれをチーフス・スペシャル」に更新されたという記述からも、いわゆる「制服警察官」の皇宮護衛官がチーフス → レギュレーションポリス → ミリポリビクトリー?に代替されても、いわゆる「SP」的な任務を与えられている「側衛員」はブローニングを使用し続けられたと考えられる。
皇宮警察史はつづける。
「日本人の体格に合うよう若干小型化し、しかも性能もすぐれた「ニューナンブ」をわが国で製作し、国産の「ニューナンブ」を製作。皇宮警察でも四十四年十二月二十六日、二十二丁を採用し、儀仗隊員に携帯させ、以降徐々に増加させている」
以上の記述からも皇宮警察ではニューナンブM60の採用は、制式化された昭和35年から9年も経った昭和44年(1969年)からであることがわかり、新けん銃への切り替えも一斉ではなく「徐々に増加」。つまり、昭和44年以降も米軍軍用回転式けん銃と併用されたことが伺えるが、昭和天皇が崩御された際の「大喪の礼」警備では、ニューナンブ以外の旧型けん銃を携行する護衛官が多数目撃されており「皇宮警察史」のいう「昭和31年同一銃種による整一化を期した」という「整一化」が、「現場の護衛官」を指すのか?「皇宮警察全体」を指すのか?はっきりせず、後年までに整一化が完了したかについては――はなはだ疑問が残る。

参考。近年撮影された「32ワルサーPPK」を携行する制服姿の皇宮護衛官。皇宮護衛官のけん銃つりひもは伝統的に臙脂色のものが用いられている。
しかし、そのなかでも各県警本部史などの資料を突き合わせると「実包の共通化」を図るべく、雑多なけん銃と弾薬のうち、45口径をその大きさと重さから敬遠し、弾種を「38SPL」で統一しようとしていたフシがあり、ニューナンブとの使用弾薬が共通であることから、近年までミリポリビクトリーモデルが日本警察では使用され続け、さらに「操作、動作の異なるコルト式けん銃の評判は良くなかった」ということからも、「皇宮警察史」のいう「昭和31年の米軍軍用回転式拳銃による同一銃種による整一化」は日本警察に大量に譲渡(当初は貸与)されたS&W ミリタリーポリスビクトリーモデルであったと考えられるが、戦後にわざわざ輸入した「チーフス」はどこへ行ったのか?その後に導入されたS&W レギュレーションポリスの行方は?それらは他本部へ管理替え?――と、ひとつの事実がわかれば新たな謎がやっぱり生まれる戦後警察けん銃の調査なのであった。