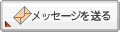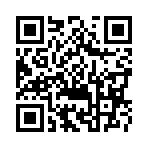楽しみながら強くなれる!田村装備開発(株)の『ガチタマTV』!
2013年05月30日
「沖縄」のカービン
やっとこ書き上げた記事がうっかり消えて、目の前真っ白になった堂主です。
「特殊銃(ゴールデンベア)導入前に「特殊銃に相当する長物」を日本警察は装備していたのか?」
という各方面からの疑問にこたえて調査。その中間報告。
「特殊銃(ゴールデンベア)は、金嬉老事件をきっかけに全国警察本部で整備され、本県にも配備された」と、千葉県警察史の記す「特殊銃導入の顛末」。金嬉老事件が発生したのは1968年(昭和43年)2月20日。この昭和43年以前に「日本警察が長物を持っていたか?」といえば、広い意味で持ってはいた――ともいえるが、その背景は複雑だ。

「1972年(昭和47年)5月 先島(宮古島・石垣島)へ現金輸送」
「沖縄県警察10年の歩み(沖縄県警察本部)」に掲載されている写真のなかの警察官の肩には紛れもなくM1カービンが写っている。

拡大した写真のなかで振り返る警察官の腰にはガバメント。米軍からけん銃とともに貸与(その後に供与)されたと考えられる米軍用のM1916ホルスターでガバメントを携行していた様子がわかるが、M1916ホルスターの弾帯にひっかけるワイヤーでは警察官用の帯革には取り付けられないことから、帯革とホルスターの間に「騎兵用」のようなアタッチメントを介して取り付けていたことがわかる。
これらのカービン銃やけん銃は1945年(昭和20年)11月29日に、アメリカ占領下の沖縄の玉城村(たまぐすくそん。現・南城市)で、アメリカ兵による婦女暴行を阻止しようとした警察官が米兵に殺害された「玉城村警察官殺害事件」などがきっかけとなっており、「1946年7月に米国軍政府は民警察官の銃器使用を認めることとし、米軍の軍用拳銃とカービン銃(米国製M1カービン)が沖縄民警察(1946年2月発足)に貸与された。日本本土の警察とは異なり常時の携行ではなく、緊急時や所属長の許可を得た場合に使用するものとなった」とされ、この際に沖縄民警察部に貸与された小火器は、本土の警察に対する貸与と同じく、その後、供与に切り替わり、長年装備され続けたと考えられ、1952年(昭和27年)4月1日の琉球警察本部設置後もカービン銃は引き継がれた。
しかし、wikipedia「琉球警察」の脚注では、
「本土の警察と異なり、銃器の常時携帯をせず装備数が限られていた代わりに、拳銃の他にカービン銃(米国製M1カービン)を装備に含んでいた。拳銃・カービン銃は、当初、沖縄住民への米軍関係者による性犯罪等の凶悪犯罪の抑止効果を狙って、1946年7月に米国軍政府が当時の沖縄民警察に対し警察官による使用を認めており(『写真集 沖縄戦後史』(那覇出版社 1986年)250頁)、琉球警察にも承継された。以降、カービン銃は、暴動等の集団的事件の鎮圧や、通貨切換時の通貨交換所警備、暴力団抗争事件等の銃器犯罪対策等の用途に本土復帰まで使用された。本土復帰後はカービン銃を廃し、他都道府県警察と同様、拳銃の常時携帯がなされるようになった。」
との記述があるが、引用元の資料をあたれていないため、詳細は不明であるが、wikipedia脚注の記述が正しい場合、「沖縄返還を機に(沖縄県警察本部発足時?)にカービン銃は廃止。警察官のけん銃の常時携行が行われた」ということとなり、「沖縄のカービン」は沖縄の本土復帰の際の「円ドル交換輸送警備」が最後の奉公の場となった可能性が高い。

※ 通貨交換は58年のドル交換以来で、カービン銃武装の警官隊約400人が軍港から日本銀行那覇支店まで警備、武装した米軍憲兵隊も出動した(1972年5月2日)
またこれらのカービン銃は返還前の沖縄では度々警察官に携帯されていたようで、終戦後まで「博徒・テキヤ」といった「ヤクザ」の概念のなかった沖縄では終戦後に「アシバ―」と呼ばれる遊び人や、「戦果アギャー」と呼ばれた強盗団。台湾・香港などと密貿易を行っていた組織などがベースとなって、その後の「沖縄ヤクザ」の源流となる組織が形成されていった。
これらの組織は米軍基地と、その周辺に形成された繁華街の利権を巡って度々、凄惨な抗争事件を起こし、これらの抗争事件で警戒などにあたる琉球警察当時の警察官――警視庁や大阪府警で訓練を受け、制服などの服制も警察庁の規定に準じていた――が、M1カービンを手に抗争を警戒したという。
「制服警察官がカービン銃」という沖縄の事情。
沖縄県警。その前身の琉球警察、さらにその前身の民警察と、一度、完全に敗戦、占領で警察機構が完全に解体されていることから、「基地の島」という背景と合わさって沖縄の警察組織は一種、独特な歴史を持っている。
現在も「基地に逃げ込まれる(=日米地位協定が立ちふさがる)前に容疑者を確保」するため、沖縄県警では米軍関係者による犯罪の初動捜査に当たる全国唯一の組織として「渉外機動警ら隊」(渉警隊)を持っており、その特殊性はいまも昔も変わらない。
この動画は「昨年、暴力団組員と間違えられ射殺された高校生」のくだりから1990年(平成元年)に放送されたものと特定出来る。「渉警 SPECIAL POLICE」と刺繍された紫の腕章を巻いて沖縄の繁華街を駆け回る渉警隊の密着取材。1990年~92年にわたってつづいた第6次沖縄抗争の警戒警備の様子が伺い知れて興味深い。
しかし、沖縄の警察の歴史を少し調べただけでも米兵による「女性対象暴力」のあまりの多さ。警察官への暴行、殺人。「遊び半分で農作業中の住民を狙撃」――と、戦後沖縄史を斜め読みするだけで、「左巻き」でなくとも沖縄県民の持つ反基地感情は理解できる。ここは政治や時事問題を語る場所ではないので省略するが、「趣味」の目線からも透けて見える戦後沖縄の歴史はまこと悲哀の連続だ。
「特殊銃(ゴールデンベア)導入前に「特殊銃に相当する長物」を日本警察は装備していたのか?」
という各方面からの疑問にこたえて調査。その中間報告。
「特殊銃(ゴールデンベア)は、金嬉老事件をきっかけに全国警察本部で整備され、本県にも配備された」と、千葉県警察史の記す「特殊銃導入の顛末」。金嬉老事件が発生したのは1968年(昭和43年)2月20日。この昭和43年以前に「日本警察が長物を持っていたか?」といえば、広い意味で持ってはいた――ともいえるが、その背景は複雑だ。
「1972年(昭和47年)5月 先島(宮古島・石垣島)へ現金輸送」
「沖縄県警察10年の歩み(沖縄県警察本部)」に掲載されている写真のなかの警察官の肩には紛れもなくM1カービンが写っている。
拡大した写真のなかで振り返る警察官の腰にはガバメント。米軍からけん銃とともに貸与(その後に供与)されたと考えられる米軍用のM1916ホルスターでガバメントを携行していた様子がわかるが、M1916ホルスターの弾帯にひっかけるワイヤーでは警察官用の帯革には取り付けられないことから、帯革とホルスターの間に「騎兵用」のようなアタッチメントを介して取り付けていたことがわかる。
これらのカービン銃やけん銃は1945年(昭和20年)11月29日に、アメリカ占領下の沖縄の玉城村(たまぐすくそん。現・南城市)で、アメリカ兵による婦女暴行を阻止しようとした警察官が米兵に殺害された「玉城村警察官殺害事件」などがきっかけとなっており、「1946年7月に米国軍政府は民警察官の銃器使用を認めることとし、米軍の軍用拳銃とカービン銃(米国製M1カービン)が沖縄民警察(1946年2月発足)に貸与された。日本本土の警察とは異なり常時の携行ではなく、緊急時や所属長の許可を得た場合に使用するものとなった」とされ、この際に沖縄民警察部に貸与された小火器は、本土の警察に対する貸与と同じく、その後、供与に切り替わり、長年装備され続けたと考えられ、1952年(昭和27年)4月1日の琉球警察本部設置後もカービン銃は引き継がれた。
しかし、wikipedia「琉球警察」の脚注では、
「本土の警察と異なり、銃器の常時携帯をせず装備数が限られていた代わりに、拳銃の他にカービン銃(米国製M1カービン)を装備に含んでいた。拳銃・カービン銃は、当初、沖縄住民への米軍関係者による性犯罪等の凶悪犯罪の抑止効果を狙って、1946年7月に米国軍政府が当時の沖縄民警察に対し警察官による使用を認めており(『写真集 沖縄戦後史』(那覇出版社 1986年)250頁)、琉球警察にも承継された。以降、カービン銃は、暴動等の集団的事件の鎮圧や、通貨切換時の通貨交換所警備、暴力団抗争事件等の銃器犯罪対策等の用途に本土復帰まで使用された。本土復帰後はカービン銃を廃し、他都道府県警察と同様、拳銃の常時携帯がなされるようになった。」
との記述があるが、引用元の資料をあたれていないため、詳細は不明であるが、wikipedia脚注の記述が正しい場合、「沖縄返還を機に(沖縄県警察本部発足時?)にカービン銃は廃止。警察官のけん銃の常時携行が行われた」ということとなり、「沖縄のカービン」は沖縄の本土復帰の際の「円ドル交換輸送警備」が最後の奉公の場となった可能性が高い。

※ 通貨交換は58年のドル交換以来で、カービン銃武装の警官隊約400人が軍港から日本銀行那覇支店まで警備、武装した米軍憲兵隊も出動した(1972年5月2日)
またこれらのカービン銃は返還前の沖縄では度々警察官に携帯されていたようで、終戦後まで「博徒・テキヤ」といった「ヤクザ」の概念のなかった沖縄では終戦後に「アシバ―」と呼ばれる遊び人や、「戦果アギャー」と呼ばれた強盗団。台湾・香港などと密貿易を行っていた組織などがベースとなって、その後の「沖縄ヤクザ」の源流となる組織が形成されていった。
これらの組織は米軍基地と、その周辺に形成された繁華街の利権を巡って度々、凄惨な抗争事件を起こし、これらの抗争事件で警戒などにあたる琉球警察当時の警察官――警視庁や大阪府警で訓練を受け、制服などの服制も警察庁の規定に準じていた――が、M1カービンを手に抗争を警戒したという。
「制服警察官がカービン銃」という沖縄の事情。
沖縄県警。その前身の琉球警察、さらにその前身の民警察と、一度、完全に敗戦、占領で警察機構が完全に解体されていることから、「基地の島」という背景と合わさって沖縄の警察組織は一種、独特な歴史を持っている。
現在も「基地に逃げ込まれる(=日米地位協定が立ちふさがる)前に容疑者を確保」するため、沖縄県警では米軍関係者による犯罪の初動捜査に当たる全国唯一の組織として「渉外機動警ら隊」(渉警隊)を持っており、その特殊性はいまも昔も変わらない。
この動画は「昨年、暴力団組員と間違えられ射殺された高校生」のくだりから1990年(平成元年)に放送されたものと特定出来る。「渉警 SPECIAL POLICE」と刺繍された紫の腕章を巻いて沖縄の繁華街を駆け回る渉警隊の密着取材。1990年~92年にわたってつづいた第6次沖縄抗争の警戒警備の様子が伺い知れて興味深い。
しかし、沖縄の警察の歴史を少し調べただけでも米兵による「女性対象暴力」のあまりの多さ。警察官への暴行、殺人。「遊び半分で農作業中の住民を狙撃」――と、戦後沖縄史を斜め読みするだけで、「左巻き」でなくとも沖縄県民の持つ反基地感情は理解できる。ここは政治や時事問題を語る場所ではないので省略するが、「趣味」の目線からも透けて見える戦後沖縄の歴史はまこと悲哀の連続だ。
Posted by アホ支群本部 at 17:26│Comments(2)
│調査研究
この記事へのコメント
久々の更新乙です。
個人的にはこのM1カービンがその後、どんな末路を辿ったのかが気になります。
米軍に返却されたか、日本側で処分したのか、今も何処かに保管されているのか?
気になります。
個人的にはこのM1カービンがその後、どんな末路を辿ったのかが気になります。
米軍に返却されたか、日本側で処分したのか、今も何処かに保管されているのか?
気になります。
Posted by やまさん at 2013年05月30日 17:49
決定的な資料は見つかっていませんが、本土の警察に貸与された米国貸与けん銃も途中で「供与」に切り変わっていますから、カービンも沖縄県警側で処分したのでは――と、考えますが、気になるところです。
しかし改めて43盛夏でカービンはシブすぎますね。
しかし改めて43盛夏でカービンはシブすぎますね。
Posted by 平和堂 at 2013年05月30日 23:54
at 2013年05月30日 23:54
 at 2013年05月30日 23:54
at 2013年05月30日 23:54※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |