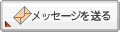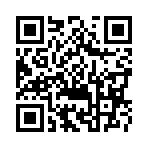2012年12月20日
ニューナンブけん銃入れについて
「日本警察」のシンボルともいうべき戦後国産けん銃第一号のニューナンブM60。
少し前まで「制服」の外勤警察官といえばほぼニューナンブであったが、その後に導入されたM37エアウェイト、M360Jサクラ等に更新されて、外勤警察官の腰からぶら下がる姿を見ることも少なくなってきたが、現行の「新制服」への切り替え前はエアウェイトも装備されてはいなかったことから、昭和後期ではニューナンブが数の上では主力けん銃として使用され、チーフス、ミリポリなどと共に使用されていた。
「新制服」切替とともにニューナンブ用けん銃入れもいっせいに新型に更新されたが、旧型は南部十四年式、二十六年式用拳銃嚢などの旧軍拳銃嚢などと共通する、型押しで絞り出されたけん銃のグリップのすべてが隠れる「クラムシェル型」のフルフラップを持っており、「ニューナンブ」と聞いて、真っ先にこのホルスターを連想する「昭和生まれ」も多いかと思う。
しかし、このニューナンブ用の蓋付きけん銃入れも調べ出すときりがなく、便宜上名称をつければ、
・「県警型」 蓋の上端が直線的な意匠
・「警視庁型」 蓋の上端が銃把(グリップ)に沿って斜めの意匠

※ 左 「県警型 一般用」 右 「警視庁型 乗車用」
以上の特徴を持つ「県警型」と、「警視庁型」に分けられ、「警視庁型」は、けん銃のグリップに合わせて蓋自体が斜めに切られ、全体的にけん銃入れを小型、軽量化されている。また「県警型」でも、
「昔から大まかな規格は決まっていても、各県警で微妙に仕様が異なっていて、試作したものを県警が警察庁にお伺いを立てて承認されたものが納入されていた」(元・装備品製造メーカー)
といい、けん銃ケース自体の縫製もミシンか、手縫いかといった違いがあり、特徴的な蓋も丸みを帯びたものから、鋭角な形状のもの。蓋自体が一回り大きいミリポリ用などに近い大きさを持つものなど、細かな仕様や製作したメーカーによる違いが顕著で興味深い。今回は復刻版製作の参考に各方面よりお借りした実物を基に比較。

上記の写真は神奈川県警?の払い下げ品とされる、いわゆる「県警型」のもので、「ニューナンブ用けん銃入れ」として、このタイプを連想する人も多いかと思う。この県警型にも大きく分けて、帯革固定部分がホルスターの袋部分に直接縫い込まれた「一般用」と、自動車警ら隊など、車両に乗降する際に邪魔にならないようにけん銃入れの角度を調整できる「乗車用」が存在する。


※ 上掲の二点とも 左 「県警型乗車用」 右 「県警型一般用」

※ 大阪府警?払下げとされる「県警型」は他のものよりも大きめの蓋が付けられ、横方向で2cm程度大きい。

※左 「県警型 一般用 (大阪?)」 右 「県警型 一般用 (神奈川?)」
これらのうち、乗車用はとくに手間がかかっており、角度調整用のロック機能のつけられた金具を帯革取り付け部分と、けん銃入れ本体の間に縫い込んであり、負荷のかかる部分のため、相当強靭な皮革を使っていて、縫い糸も番手の最も太い糸で、職人がひとつひとつ縫い上げている。「外勤警察官用の実用品」として作られてはいるが、「実用品として頑丈であることと同時に、警察官としての威厳を持たせることを要求されていたため、造りもおのずと手間暇のかかる方法となった」(元・装備品製造メーカー)という。蓋の造型、けん銃入れ本体の微妙な曲線など、各所にまさに職人技と呼べる手間暇がかけられ、相当なコストもかけられている。
これらの「蓋付きけん銃ケース」は警察官の服制について規定した公安委員会規則の一部が改正された昭和48年(1973年)6月以降に、改正以前から使われていた「ニューナンブけん銃ケース 蓋なし」に代わって製造されたもので、平成6年(1994年)の現行の服装規則へ変更されるまでの20年余り製造されており、「乗車用」が蓋つきけん銃入れの製造開始当初から存在したのか、途中から導入されたのか、はたまた「一般型」と「乗車型」が平成6年まで並行して使用されたのかなどの詳細は不明だ。
「警視庁は予算規模も大きく「首都を守る」という誇りもあったのか、現場警察官からの装備改善の要望を積極的に聞いており、装備品の改良に熱心だった。旧制服の時代にはほかの県警と異なる警棒吊りやけん銃入れを使っていたし、警察庁の規定とはまったく異なる規格を制定。のちに警察庁が警視庁の型を制式化するなどということもあって、他県警と比べて予算も多く持っていたことも大きいが、装備品はいまも昔も独自のものが多かった」(元・払下げ業者)
その「最たるもの」が、「ニューナンブけん銃入れ (警視庁型)」であったという。

前出の様に「警視庁型」は県警型と異なり、蓋の上部が銃把(グリップ)に合わせて斜めにカットされており、「腰の大砲」を携行する上で、無駄なスペースがなくなった分、小型化されて携行しやすいように改良されている。


※ 左 「県警型」 右 「警視庁型」
県警型と比較してみると、全体的な造りが一般的な県警型よりもタイトになっていて、けん銃ケースの袋部分の全長も短くなり、少しでも小型、軽量化しようとした様子が伺える。けん銃ケース自体も二十六年式拳銃嚢とよく似ており、「警視庁型」の導入されたころには旧日本軍の装備品を製作。戦後は警察向けの装備品を多く納入していたメーカーも健在な頃で、「警視庁型」導入の背景にはこのような事情も関係していたのかもしれない。
しかし、この警視庁型の蓋ひとつとっても、「威厳を持たせる」一環か、非常に手の込んだ成形方法で繊細に型絞りされている。この型を使った「絞り」と呼ばれる成形技術は皮革製造メーカーの腕が如実に出る部分で、蓋自体が湾曲しているため、プレスによる打ち抜きが出来ないため、おのずと職人による手作業での切り出しとなり、コスト的にも、技術的にも高くつく。「現代的なコスト感覚ではなかなか作れないシロモノ。作ることが出来る業者も限られてくる」(皮革業者)という。
そして、改めて見てみると、けん銃入れの蓋の上端ギリギリに銃把(グリップ)が当たるように作られていて、けん銃自体をけん銃入れ本体にとめる「安全止革」の寸法も長年の使用で伸びないようにかなりタイトに作られ、この「ダブルロック」から使い込んだけん銃入れでも、ホルスターのなかでけん銃が暴れてまかり間違っても脱落しないように1mm単位の誤差も出ないようにタイトに作られている。「ニューナンブ 警視庁型」ひとつとっても、当時の物作りが、非常に手の込んだ「実用品離れ」した工芸品的な手順で製作されていたことがうかがえ興味深い。
しかし、かつては警備用品として払い下げ品店で売られた外勤警察官の装備品も、民間での需要のない(←あっても困る)「けん銃入れ」とあって、その多くは払い下げられても、
「警察のホルスターはいい革を使っているので火のつきがいい」(元・払下げ業者)
と、これらの「工芸品」も、風呂屋の薪がわりに下町の風呂屋にトラック満載で運び込まれて、年中、燃やされ、またあるものは埋め立て地の造成で東京湾の処理場に埋められたという。
「払い下げられたホルスターのうち、状態のいい物などのごく一部が映画制作会社や映画小道具のレンタル会社に売られ、撮影用に使われた」(元・払下げ業者)
ここに集まったけん銃入れもこのようにして「生き残った」ものの一部と言えそうだ。
そして、そうやって映画制作会社などに渡ったけん銃入れも長年の使用で損耗し、手間暇のかかる製法上、なかなか複製が作れず、映画関係者も代用品に頭を抱えていると伝え聞く。趣味世界でもいくつもの「ニューナンブ用ホルスターのレプリカ」は作られたが、どれも工程や材質を簡略化した現行初期型を模したもので、旧型けん銃入れが作られなかった背景には「複製を作ろうにもコスト的にも厳しく、作れる職人自体が鬼籍入り」(映像制作会社関係者)このような理由もあったという。
「けん銃入れ」ひとつとっても、その背景には時代が見えてなかなか面白い。しかし、日本刀の時代から、三八式小銃の槓桿(ボルト)後部の彫刻など、「武器としては不要な装飾」に心血を注いだ旧日本軍。そして、戦後の「民主警察」に至るまで「武器という実用品に美を求める」日本人の気風は変わっていないのだなと、感じさせられる「ニューナンブけん銃入れ」調査であった。
少し前まで「制服」の外勤警察官といえばほぼニューナンブであったが、その後に導入されたM37エアウェイト、M360Jサクラ等に更新されて、外勤警察官の腰からぶら下がる姿を見ることも少なくなってきたが、現行の「新制服」への切り替え前はエアウェイトも装備されてはいなかったことから、昭和後期ではニューナンブが数の上では主力けん銃として使用され、チーフス、ミリポリなどと共に使用されていた。
「新制服」切替とともにニューナンブ用けん銃入れもいっせいに新型に更新されたが、旧型は南部十四年式、二十六年式用拳銃嚢などの旧軍拳銃嚢などと共通する、型押しで絞り出されたけん銃のグリップのすべてが隠れる「クラムシェル型」のフルフラップを持っており、「ニューナンブ」と聞いて、真っ先にこのホルスターを連想する「昭和生まれ」も多いかと思う。
しかし、このニューナンブ用の蓋付きけん銃入れも調べ出すときりがなく、便宜上名称をつければ、
・「県警型」 蓋の上端が直線的な意匠
・「警視庁型」 蓋の上端が銃把(グリップ)に沿って斜めの意匠
※ 左 「県警型 一般用」 右 「警視庁型 乗車用」
以上の特徴を持つ「県警型」と、「警視庁型」に分けられ、「警視庁型」は、けん銃のグリップに合わせて蓋自体が斜めに切られ、全体的にけん銃入れを小型、軽量化されている。また「県警型」でも、
「昔から大まかな規格は決まっていても、各県警で微妙に仕様が異なっていて、試作したものを県警が警察庁にお伺いを立てて承認されたものが納入されていた」(元・装備品製造メーカー)
といい、けん銃ケース自体の縫製もミシンか、手縫いかといった違いがあり、特徴的な蓋も丸みを帯びたものから、鋭角な形状のもの。蓋自体が一回り大きいミリポリ用などに近い大きさを持つものなど、細かな仕様や製作したメーカーによる違いが顕著で興味深い。今回は復刻版製作の参考に各方面よりお借りした実物を基に比較。
上記の写真は神奈川県警?の払い下げ品とされる、いわゆる「県警型」のもので、「ニューナンブ用けん銃入れ」として、このタイプを連想する人も多いかと思う。この県警型にも大きく分けて、帯革固定部分がホルスターの袋部分に直接縫い込まれた「一般用」と、自動車警ら隊など、車両に乗降する際に邪魔にならないようにけん銃入れの角度を調整できる「乗車用」が存在する。
※ 上掲の二点とも 左 「県警型乗車用」 右 「県警型一般用」
※ 大阪府警?払下げとされる「県警型」は他のものよりも大きめの蓋が付けられ、横方向で2cm程度大きい。
※左 「県警型 一般用 (大阪?)」 右 「県警型 一般用 (神奈川?)」
これらのうち、乗車用はとくに手間がかかっており、角度調整用のロック機能のつけられた金具を帯革取り付け部分と、けん銃入れ本体の間に縫い込んであり、負荷のかかる部分のため、相当強靭な皮革を使っていて、縫い糸も番手の最も太い糸で、職人がひとつひとつ縫い上げている。「外勤警察官用の実用品」として作られてはいるが、「実用品として頑丈であることと同時に、警察官としての威厳を持たせることを要求されていたため、造りもおのずと手間暇のかかる方法となった」(元・装備品製造メーカー)という。蓋の造型、けん銃入れ本体の微妙な曲線など、各所にまさに職人技と呼べる手間暇がかけられ、相当なコストもかけられている。
これらの「蓋付きけん銃ケース」は警察官の服制について規定した公安委員会規則の一部が改正された昭和48年(1973年)6月以降に、改正以前から使われていた「ニューナンブけん銃ケース 蓋なし」に代わって製造されたもので、平成6年(1994年)の現行の服装規則へ変更されるまでの20年余り製造されており、「乗車用」が蓋つきけん銃入れの製造開始当初から存在したのか、途中から導入されたのか、はたまた「一般型」と「乗車型」が平成6年まで並行して使用されたのかなどの詳細は不明だ。
「警視庁は予算規模も大きく「首都を守る」という誇りもあったのか、現場警察官からの装備改善の要望を積極的に聞いており、装備品の改良に熱心だった。旧制服の時代にはほかの県警と異なる警棒吊りやけん銃入れを使っていたし、警察庁の規定とはまったく異なる規格を制定。のちに警察庁が警視庁の型を制式化するなどということもあって、他県警と比べて予算も多く持っていたことも大きいが、装備品はいまも昔も独自のものが多かった」(元・払下げ業者)
その「最たるもの」が、「ニューナンブけん銃入れ (警視庁型)」であったという。

前出の様に「警視庁型」は県警型と異なり、蓋の上部が銃把(グリップ)に合わせて斜めにカットされており、「腰の大砲」を携行する上で、無駄なスペースがなくなった分、小型化されて携行しやすいように改良されている。
※ 左 「県警型」 右 「警視庁型」
県警型と比較してみると、全体的な造りが一般的な県警型よりもタイトになっていて、けん銃ケースの袋部分の全長も短くなり、少しでも小型、軽量化しようとした様子が伺える。けん銃ケース自体も二十六年式拳銃嚢とよく似ており、「警視庁型」の導入されたころには旧日本軍の装備品を製作。戦後は警察向けの装備品を多く納入していたメーカーも健在な頃で、「警視庁型」導入の背景にはこのような事情も関係していたのかもしれない。
しかし、この警視庁型の蓋ひとつとっても、「威厳を持たせる」一環か、非常に手の込んだ成形方法で繊細に型絞りされている。この型を使った「絞り」と呼ばれる成形技術は皮革製造メーカーの腕が如実に出る部分で、蓋自体が湾曲しているため、プレスによる打ち抜きが出来ないため、おのずと職人による手作業での切り出しとなり、コスト的にも、技術的にも高くつく。「現代的なコスト感覚ではなかなか作れないシロモノ。作ることが出来る業者も限られてくる」(皮革業者)という。
そして、改めて見てみると、けん銃入れの蓋の上端ギリギリに銃把(グリップ)が当たるように作られていて、けん銃自体をけん銃入れ本体にとめる「安全止革」の寸法も長年の使用で伸びないようにかなりタイトに作られ、この「ダブルロック」から使い込んだけん銃入れでも、ホルスターのなかでけん銃が暴れてまかり間違っても脱落しないように1mm単位の誤差も出ないようにタイトに作られている。「ニューナンブ 警視庁型」ひとつとっても、当時の物作りが、非常に手の込んだ「実用品離れ」した工芸品的な手順で製作されていたことがうかがえ興味深い。
しかし、かつては警備用品として払い下げ品店で売られた外勤警察官の装備品も、民間での需要のない(←あっても困る)「けん銃入れ」とあって、その多くは払い下げられても、
「警察のホルスターはいい革を使っているので火のつきがいい」(元・払下げ業者)
と、これらの「工芸品」も、風呂屋の薪がわりに下町の風呂屋にトラック満載で運び込まれて、年中、燃やされ、またあるものは埋め立て地の造成で東京湾の処理場に埋められたという。
「払い下げられたホルスターのうち、状態のいい物などのごく一部が映画制作会社や映画小道具のレンタル会社に売られ、撮影用に使われた」(元・払下げ業者)
ここに集まったけん銃入れもこのようにして「生き残った」ものの一部と言えそうだ。
そして、そうやって映画制作会社などに渡ったけん銃入れも長年の使用で損耗し、手間暇のかかる製法上、なかなか複製が作れず、映画関係者も代用品に頭を抱えていると伝え聞く。趣味世界でもいくつもの「ニューナンブ用ホルスターのレプリカ」は作られたが、どれも工程や材質を簡略化した現行初期型を模したもので、旧型けん銃入れが作られなかった背景には「複製を作ろうにもコスト的にも厳しく、作れる職人自体が鬼籍入り」(映像制作会社関係者)このような理由もあったという。
「けん銃入れ」ひとつとっても、その背景には時代が見えてなかなか面白い。しかし、日本刀の時代から、三八式小銃の槓桿(ボルト)後部の彫刻など、「武器としては不要な装飾」に心血を注いだ旧日本軍。そして、戦後の「民主警察」に至るまで「武器という実用品に美を求める」日本人の気風は変わっていないのだなと、感じさせられる「ニューナンブけん銃入れ」調査であった。
Posted by アホ支群本部 at 21:37│Comments(2)
│調査研究
この記事へのコメント
威厳もあるでしょうが、盗難防止や雨風による銃の腐食を防ぐ為にも蓋付きが合理的だったという考えがあったんだろうと思います。
Posted by やまさん at 2012年12月20日 23:55
お世話になっております。
各県警史を調べても、「盗難と汚損防止の観点から蓋つきとした」との記述が散見され、これらの理由(実用性)と共に装飾(威厳)的なものを含ませた――ということなのでしょうね。
しかし、複製製作を結果的に断られた業者の職人さんたちも、「昔の警察は本当に手間とカネのかかった装備を入れてたんだなぁ」と、感嘆まじりに眺めまわしているのが印象的でした。
各県警史を調べても、「盗難と汚損防止の観点から蓋つきとした」との記述が散見され、これらの理由(実用性)と共に装飾(威厳)的なものを含ませた――ということなのでしょうね。
しかし、複製製作を結果的に断られた業者の職人さんたちも、「昔の警察は本当に手間とカネのかかった装備を入れてたんだなぁ」と、感嘆まじりに眺めまわしているのが印象的でした。
Posted by 平和堂 at 2012年12月20日 23:59
at 2012年12月20日 23:59
 at 2012年12月20日 23:59
at 2012年12月20日 23:59※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。